家計簿は家計の収入、支出を把握するのに必要不可欠ですが、どうやって記録してますか? この記事では、様々ある家計簿のつけ方を網羅的に比較したうえで、一番生産性の高い家計簿の付け方について解説します。
対象読者
- 家計簿をつけるのが面倒に思っている
- 手間ひまをあまりかけずに家計改善したい方
この記事で分かること
- 家計簿のつけ方の選び方のポイント
- 生産性の高い家計簿のつけ方
一番生産性の高い家計簿のつけ方は
家計簿をつける手間がかからず、家計の現状把握や課題抽出ができ、効果が高い方法は、ズバリ、Moneyforward MEなどの家計管理アプリを使うことです。
以下では、家計簿をつけるさまざまな方法を紹介したのち、その方法を比較して、なぜ家計管理アプリを使う方法がよいのかを解説します。
家計簿の目的
そもそも家計簿をつける目的は何でしょうか?それは、家計の収入と支出の現状把握したり、家計の課題を抽出したり、支出コントロールしたりするためです。
なぜわざわざこんなこというかというと、家計簿をつけること自体が目的化しがちだからです。すなわち、家計簿をつけるのは目的ではなく、家計の現状把握・課題抽出・打ち手実行(支出コントロール)の手段ということです。
家計簿に求める要件
家計簿の目的を踏まえた上で家計簿に求める要件は何でしょうか?
家計簿により何を実現したいかというと、家計の現状把握や課題抽出をしたい、家計のコントロールしたいという点があげられますね。
家計の現状把握には、費目ごとの支出額がわかることが必要です。人によっては費目を自由にできたほうが家計管理しやすい場合もあるので、カスタマイズできる点もあったほうがよい場合もあります。
また、分析して家計の課題を抽出するには、費目ごとの集計額が過去の値や平均値と比較できたり推移をグラフ化できるのが望ましいです。また、支出のコントロールするには、現在までの支出額がリアルタイムで見えることが必要です。
また、家計簿のベネフィットがあっても手間がかかると実行できませんね。特に、夫婦共働きで子育て中だと時間がとても貴重です。そのため、家計簿をつける手間がすくなくて、コストパフォーマンス(ここでは、少ない手間で家計管理の現状把握や分析ができること)が高い点も求められます。
これらを踏まえると下記の5つの要件が挙げられます。
- 費目ごとの集計の手間が少ない
- 現状把握するためには、個々の支出ではなく、どんな費目にどれだけ使われているかの把握が基本となります。そのため、費目ごとの集計が出しやすいのが必要となります。
- 分析しやすく課題抽出しやすい
- 家計の分析は、前月や平均値、前年同月比と比較したり、支出全体に占める各費目の比率を見たりすることが多いです。そのため、これらが把握しやすい、例えば、グラフなどで可視化しやすいのが望ましいです。
- リアルタイムでの各費目の支出額がわかる
- 家計をコントロールするには、できるだけリアルタイムで現状の支出額がわかる方がよいですね。早く把握できるとその分支出を抑えるための具体的行動を早くとることができるからです。
- 記録や費目分類の手間が少なく、継続しやすい
- 家計簿は必要性をわかっていても継続できない人が多いのは、手間がかかるからです。その手間をできる限り減らせるのがよいですね。
- 費目の分類をカスタマイズしやすい
- お金の使い方は、人さまざまであり、家計管理も自由な費目で管理したい場合があるかもしれません。例えば、外食費用は多くの場合食費に分類されますが、娯楽費として扱いたい人もいます。
家計簿をつける手段
次に、具体的な家計簿のつけ方について見ていきます。世の中には本当に様々な家計簿のやり方があります。ここでは、以下のようにポイントを抑えつつ分類してみます。
- 支出を記録する
- 記録のデジタル化
- 方法1 家計管理アプリ
- 方法2 Excel管理
- 記録のアナログ化
- 方法3 市販の家計簿ノート
- 方法4 手書きノート
- 記録のデジタル化
- 支出の記録つけない(残金のみ管理)
- 残金総額のみ管理
- 方法5 予算の現金おろしてまとめて管理
- 費目ごとの残金を管理
- 方法6 予算の現金袋分け管理
- 残金総額のみ管理
方法1 家計管理アプリ
最近、人気があるやり方です。アプリは様々ありますが最も代表的なのはMoneyforwardMEです。主な特徴は以下の通りです。
- クレジットカードの利用履歴や銀行口座の入出金明細と連携することで記録自体を不要にできる
- スマホアプリからレシートを撮るだけでデータ化できる
- 自動的にグラフ化してくれる
家計簿の目的である、家計収支の現状把握や課題抽出を手間をかけずにやることができます。
私も2013年頃に導入しましたが、その頃から連携先が増えたり、機能、使いやすさ、セキュリティが格段に向上してきています。

方法2 Excel管理
日々の支出を表計算ソフトのデータにして、費目ごとに集計したり、グラフ化したり、自由に分析できます。集計やグラフ化は関数使ったりすれば自動でできます。
問題点は、記録(データ化)するのが面倒なことです。レシートを見たり、クレジットカードの利用明細見たりして、費目を分類して記録は本当に手間です。
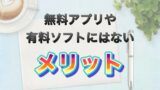
私も長男が生まれる前は、カスタマイズしやすいし、Excel使い慣れてるしでこのやり方でした。ですが、月に1回まとめて作業してましたが、どんなに早くやっても1時間ほどかかってました。主に、レシートを分類するのと、クレジットカード履歴を見て分類するのに時間がかかってました。子どもが生まれてからは時間がもったいなくてやめました。
方法3 市販の家計簿ノート
市販の家計簿ノートにも様々な種類があります。ここでは代表的な家計簿ノートのひとつである、明るい暮らしの家計簿をとりあげます。
問題点は、やはり日々の支出の記録、費目分類しての記録、月単位で集計の作業が発生する点です。また、データ化されないので分析するのも大変です。
方法4 手書き家計簿ノート
手書きの家計簿ノートを作ってやるやり方です。今はブログ等で公開しているのでそれらを真似してやることで手間かけずに導入できます。また、自由に使えるのでカスタマイズ性はよいと思います。

このやり方の問題点は、やはり記録や集計の手間がかかる点、分析しづらい点です。
方法5 現金まとめて管理
各月の予算額の現金をおろして、その現金でやりくりするやり方です。特に費目は分けないです。
問題点は何にいくら使ったかがわからなくなるし、当然課題抽出や改善は、記憶に頼ることになってしまいます。また月末あるいは給料日間際に、残額が少なくて困るというのもこのパターンですね。
方法6 現金袋分け
ブログ等でよく見かけるやり方です。各費目の予算を決めて、その予算額の現金を月初めに入れます。その月の支出はその現金から出します。クレジットカード等で払った場合はその同額を現金出す運用が多いです。

このやり方の問題点は、記録が残らないので、いつ何に使ったのかが分からない点、分析ができない点です。また、運用する上でも、記録が不要な代わりに、小銭の管理が必要になったり、現金を取り出す作業が必要になったり手間がかかります。
家計簿の付け方の比較
家計簿のつけ方を要件ごとに比較した結果を示します。
| 家計管理アプリ | Excel管理 | 市販家計簿ノート | 手書きノート | 現金一括管理 | 現金袋分け | |
| 費目集計 | ○ | ○ | △ ※1 | △ ※1 | ✕ | △ |
| 分析・課題抽出 | ○ | ○ | △ ※2 | △ ※2 | ✕ | ✕ |
| リアルタイム把握 | ○ | △ ※3 | △ ※3 | △ ※3 | ○ | ○ |
| 記録しやすさ | ○ | ✕ | ✕ | ✕ | ー | ー |
| カスタマイズ | △ ※4 | ○ | ✕ | ○ | ー | ○ |
- ※1 費目ごとの集計に電卓等で計算必要
- ※2 グラフ化したり分析するには、別途データ化作業が必要
- ※3 リアルタイムで把握するには毎回家計簿への記録、集計が必要で手間大
- ※4 MoneyforwardMEだと、大分類は変更できないが小分類は追加可能
これを見れば、よほどカスタマイズ性にこだわりがなければ、記録が自動ででき、現状把握、課題抽出といった本質的な作業にフォーカスできる家計簿アプリがおすすめです。
紙のノートをつけるのは日々の手間がかかるので、時間が貴重な夫婦共働き、子育て世帯には不向きだと考えます。
現金管理するやり方は、家計の現状把握や課題抽出には適していないです。現状把握や課題抽出した上で、予算の遂行という場合に使うのなら適しているかもしれません。ただ、現金をベースにしているので、時短のためネット通販多く利用している夫婦共働きや子育て世帯にはやはり不向きと思います。
なお、袋分けと同様の予算に基づく支出コントロールは家計管理アプリでもできます。
まとめ
この記事では夫婦共働き、子育て世帯向けに適した家計簿のつけ方について解説しました。まとめると
- 家計簿の目的は、家計の現状把握、課題抽出、実行(支出コントロール)です
- 家計簿のやり方の選ぶポイントは
- 費目集計のやりやすさ
- 分析、課題抽出しやすさ
- リアルタイムな支出把握
- 記録のしやすさ
- カスタマイズしやすさ
- 手間が少なくてベネフィットを得られるコストパフォーマンスがよい家計簿付け方は、家計管理アプリです
- 時間が貴重な夫婦共働き、子育て世帯には、最もコストパフォーマンスよい家計管理アプリの利用がおすすめ
ではでは。



コメント